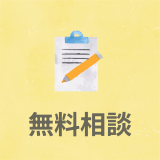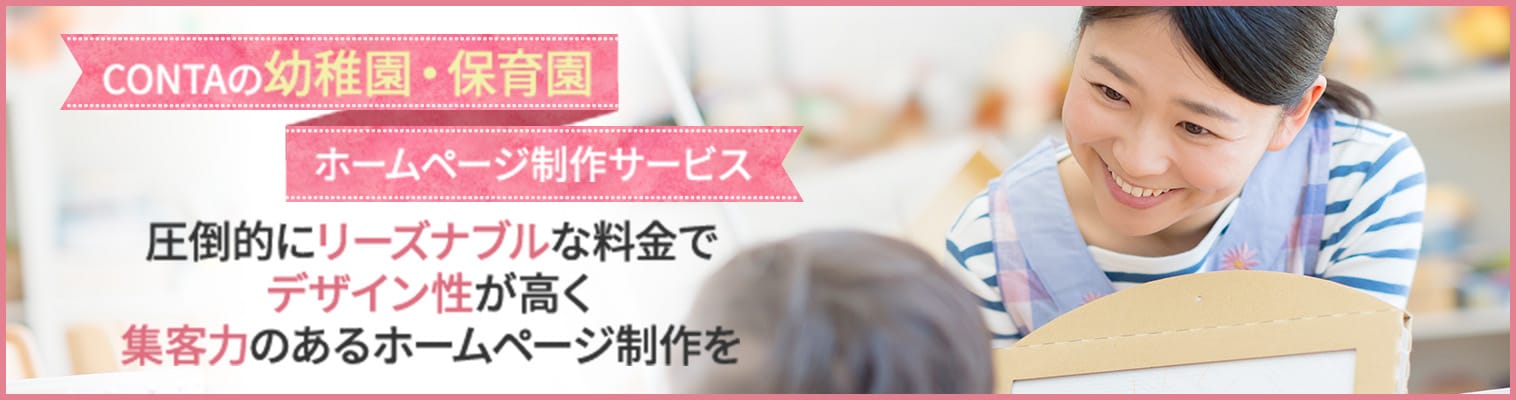-
園の特色、伝えられていますか? 保護者が知りたい情報5選と掲載例
記事の目次
はじめに:「園の特色が伝わらない」その悩み、よく聞きます
保護者にとって園を選ぶ決め手は、「安心して預けられるかどうか」。
そしてその判断材料になるのが、園のホームページです。「うちの園は●●を大事にしているのに、ホームページでは伝わっていない気がする」
「似たような園ばかりに見えて、特色が出せていない」
そんなお悩みをよく伺います。この記事では、保護者が知りたい情報をどのように伝えるべきか、5つの項目と掲載例を交えて、分かりやすく解説します。

1. 保護者が知りたい情報ベスト5と掲載例
(1)園の保育方針・理念
なぜ知りたいの?
保護者は「この園の考え方が、自分の家庭の育児と合うか」を気にしています。どう伝える?
「一人ひとりの個性を大切に」「自然の中でのびのび育つ」など、やさしい言葉でまとめましょう。
園長先生のメッセージとして掲載すると、より伝わります。掲載例:
当園では「遊び」を大切にしています。
友だちと一緒に考え、工夫し、時にはぶつかりながら成長していく過程を見守ります。(2)園児の1日の過ごし方
なぜ知りたいの?
「子どもがどんなふうに1日を過ごすのか」は、保護者の大きな関心事です。どう伝える?
時系列でシンプルに紹介し、写真やイラストがあるとイメージしやすくなります。掲載例:
9:00 登園・自由あそび
10:00 朝の会・活動(制作、散歩など)
12:00 給食
13:00 午睡(年少以下)
15:00 おやつ・帰りの会
16:00 順次降園・延長保育開始
(3)給食・アレルギー対応
なぜ知りたいの?
食は健康に直結するため、保護者の関心が高いポイントです。どう伝える?
給食の一例、手作りの取り組み、アレルギーへの対応を丁寧に説明しましょう。掲載例:
毎日園内の調理室で手作りしています。
アレルギーをお持ちのお子さまには、個別対応を行い、安全に配慮しています。
→ 実際の献立例(写真付き)を数日分掲載すると効果的です。(4)行事・イベントの紹介
なぜ知りたいの?
「どんな思い出が作れるか」「親の参加はどのくらいあるか」などを気にしています。どう伝える?
写真つきで季節ごとに紹介すると、園の雰囲気や保育の楽しさが伝わります。掲載例:
・春:親子遠足、こいのぼり制作
・夏:プール遊び、夏祭り
・秋:運動会、芋ほり
・冬:生活発表会、餅つき大会(5)施設・安全対策
なぜ知りたいの?
子どもを安心して預けられるかどうかを見極めるために、環境や安全面は重要です。どう伝える?
セキュリティや避難訓練、AEDの設置なども一言あると安心されます。掲載例:
各保育室には見守りカメラを設置し、セキュリティ面に配慮しています。
毎月避難訓練を行い、災害時の対応も職員で共有しています。
2. 情報を「やさしく・わかりやすく」伝えるポイント
専門用語を避ける
例えば「一斉保育」「縦割り保育」などの言葉は、保護者には馴染みがない場合も。
できるだけ説明をつけたり、簡単な言い回しに置き換えましょう。長文よりも、見出し+短い文章
スマホで読むことが多いため、見出しをつけて読みやすくしましょう。
箇条書きや表の活用もおすすめです。写真やイラストを積極的に活用
文字だけよりも、写真があることで一気に園のイメージが伝わります。
行事や日常の保育風景の写真を、定期的に更新できると理想的です。3. 実際に改善して効果が出た事例
【事例1】園の方針を「園長メッセージ」で伝えた園
「保育理念が見えて、共感できた」という声が増え、説明会の参加率が上がった例があります。
【事例2】行事紹介ページを充実させた園
季節ごとに子どもたちの活動写真を掲載することで、「楽しそうな園生活」が伝わり、見学予約につながりました。
【事例3】給食の写真を定期更新した園
給食をブログ形式で紹介したことで、「安心して預けられる」と好評に。SNSとも連動して認知が広がりました。
4. まとめ:園の“らしさ”は、伝え方次第で伝わります
「うちの園には自信がある。でもうまく言葉にできない」
そんな時は、まずは保護者目線で「どんな情報があれば安心か?」を考えることが第一歩です。園の特徴や雰囲気は、ほんの少しの工夫でしっかり伝えられます。
せっかくの魅力をホームページで“もったいない”ままにしないよう、一度見直してみませんか?よくある質問
- Q. 写真はどこまで載せても大丈夫ですか?
- A. 保護者の同意を取った上で顔が映らないようにするか、スタンプで加工するなどの工夫が有効です。
- Q. 園長のメッセージって何を書けばいい?
- A. 難しく考えず、保護者への想いや、子どもとの関わり方への考えを素直に書くと伝わります。
- Q. 他の園と差別化するにはどうすれば?
- A. 実際の取り組みや保護者の声など「実感のこもった情報」を掲載するのが効果的です。